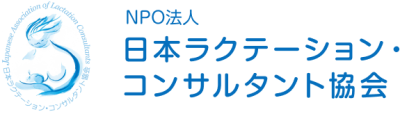ポイントは「出産後できるだけ早くから」「赤ちゃんの欲しがるサイン(下記*参照)に応えて時間や回数の制限なく」授乳することです。
母乳が作られるしくみを知るとその理由がわかりやすいです。妊娠中から産後2日目頃まで作られる初乳は、量は少ないですが赤ちゃんを感染症から守ったり、免疫の発達を助けたりする重要な役割を持ちます。その後、多くの女性で産後3日目頃に母乳の量が急激に増え成分的にもカロリーの高い母乳に変化します。そのとき鍵になるのが母乳を作る働きをする、プロラクチンというホルモンです。
プロラクチンは出産直後に血液中の濃度が最も高く、その後どんどん低下しますが授乳や搾乳の度に一時的に上昇し十分な濃度が維持されます。そのため、出産後できるだけ早くから赤ちゃんの欲しがるサインに応えてひんぱんに授乳をするか、様々な理由から赤ちゃんと離れて過ごす場合には搾乳(Q18参照)をすることが理にかなっています。プロラクチンは夜間に多く分泌されるので夜間も赤ちゃんのサインでひんぱんに授乳すると母乳育児が軌道に乗りやすいこと、お母さんをリラックスさせ眠気を誘う作用をもつことも知っておきたいです。
赤ちゃんは泣く前にもぞもぞ動く、口をパクパクさせるなどの空腹のサインを出しています。泣いてからだと赤ちゃんが焦って落ち着かない、舌が上がってしまうなどの理由から上手におっぱいに吸い付けないことが増えます。お母さんも赤ちゃんも元気なら、一日中一緒の部屋で過ごせると早めのサインに応えられるので授乳回数が自然に増え、落ち着いて授乳しやすくなります。また、痛みなくひんぱんに授乳でき、赤ちゃんが母乳を十分飲みとれるためには授乳時の抱き方や含ませ方のコツを知っておくことがとても大切なので、Q6を参考にして下さい。
入院中赤ちゃんと一日中一緒だとよく休めないのではないかしら、赤ちゃんの異常にすぐ気づけないのではないかしらと不安に思われるかもしれません。授乳とお母さんの睡眠との関係についてはQ11を参考にしてみて下さい。出産直後は母子同室でも別室でも赤ちゃんの状態が変わりやすい時期ですが、母子同室であることと赤ちゃんの急変リスクには関連がないとされています。安全に、ここちよく母子同室や授乳ができるために、妊娠中から産科施設と十分に方針を話し合う機会が持てると安心です。
*赤ちゃんの飲みたいサインhttps://llljapan.org/postpartum/
【参考文献】
- NPO法人日本ラクテーション・コンサルタント協会(2015). 母乳育児支援スタンダード第2版, 医学書院 p16, pp112-114, pp162-163
- BFHI 2009 翻訳編集委員会(2009). 赤ちゃんとお母さんにやさしい母乳育児支援ガイド ベーシック・コース 「母乳育児成功のための10か条」の実践, 医学書院 P133, pp175-180,
- World Health Organization (2009). Infant and young child feeding: model chapter for textbooks for medical students and allied medical staffs p11 https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/44117/9789241597494_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y (2024年11月9日確認)
- 一般社団法人日本周産期・新生児医学会(2019). 母子同室実施の留意点 https://www.jspnm.jp/uploads/files/guidelines/teigen190905B.pdf (2024年10月30日確認)
- NPO法人ラ・レーチェ・リーグ日本. 赤ちゃんは十分に母乳を飲んでいるかしら? https://llljapan.org/wp-content/uploads/info01.pdf (2024年12月7日確認)
【文責】山本歩 JA長野厚生連佐久医療センター(小児科医・IBCLC)
【ピアレビューアー】
黒澤かおり 中村和恵
【完成年月日】2024年12月5日
【免責】この情報は医学的な診断や治療の代替となるものではありません。詳しくはかかりつけ医とご相談ください。